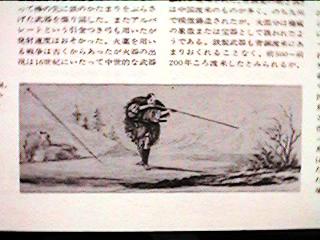2.吹き矢の歴史と文献
*吹矢健康法教本 2000.5.10 樋口裕乗 著 B5 P90 \1,200 Tel 0258-34-2303 発売中
*The textbook of sports blowgun 著者 H.Higuchi 1999.12.1 Tel 0258-34-2303発売中
-------------------------------------------------------------------------------
*人間万事吹矢的:040418
これは山東京伝 別名北尾政演(1761-1816)の書いた黄表紙本の題名です。
この本は江戸時代に流行った機関的(からくり仕掛け的)を題材にしています。
喜・・・心の矢が喜の的に当たれば大黒を出す。
怒・・・心の矢が怒の的に当たれば般若を出す。
哀・・・心の矢が哀の的に当たれば鳥刺しを出す。もちに鳥がくっついて苦しむことを意味しています。
楽・・・心の矢が楽の的に当たれば西行をだす。悟り切った境地になれば気持ちがよいと言う意味です。
題名に示すように吹矢でもからくり仕掛け的が行われてたことが分かります。
機関的は吹矢で行われていたもので、貞守漫稿には、矢が的に当たると紐がゆるんで的がはずれて
人形、妖怪、幽霊などがでるからくりがあると記載がされています。
当時の楊弓の的は四角の木の枠の中心に的が来るように的板を紐で4方向に引っ張って固定したもの
でした。多分機関的も同様な方法で的板を固定する紐が軽く結んであり、矢が当たると紐がほどけて
的板が落下する仕組みになっていたのではないかと思います。
*1.鈴木春信(1725?-1770)の描いた吹矢なえしの浮世絵。
約1mくらいの先が太い尺八型の吹矢でゲームをしている絵で大変興味深い。
江戸東京博物館http://www.tvz.com/nishiki-e/nishiki2/ni04.html(020619 040607)
*北九州市立美術館Tel 093-882-7777 F093-861-0959
に歌川国長(??-1827)の吹矢大仕掛1810-1811 錦絵 和紙 38.5x26.5cm があります。
*吹矢健康法 H3.10.15(1991)樋口 裕乗 自費出版 在庫なし
吹き矢をスポーツとして考えた史上最初の文献で、この中には矢を紙やフィルムで作る方法の
図解、スポーツ吹き矢の的、筒の長さは120cmなどの競技規則が書かれている。距離は8mと
も書かれている。この本が現代における吹矢の文献としては史上最初で現在のスポーツ吹矢の
ルールの原点になっている。
* Blowguns The Breath of Death (必殺の吹矢)1993.12.29著者Michael D.Janich
出版社:Paladin Press, P.O.Box 1307,Boulder,Colorado 80306,USA $12.00
本書の内容は熱帯地方の吹矢やワイヤの矢を使うアメリカンタイプの吹矢について、その作り方
などを記載している。吹矢の文献としては貴重だがスポーツとしての吹矢のルールなどは書かれ
ていない。ビデオもある。http://www.amazon.com をみれば購入できる。
* Sport blowguns スポーツブローガン1999著者 Amante P. Marinas,Sr.出版社
United Cutlery Corp.
アメリカで吹矢をスポーツとしてとらえた最初の本です。ワイヤ式の矢で10mから吹いている。
アマンテPマリナス氏は元フィリッピンの大学で化学の教授だった人でフィリッピン武道各種の
造詣が深い、武道の著書は多数ありバリソン(バターフライナイフ)のビデオも発売されている。
*医師がすすめる「スポ−ツ吹矢健康法」H7 1995.12.15発行 樋口裕乗 林督元共著 \1,200
この中に樋口の考えた吹き矢競技の屋内屋外のルールが書かれている。廃版在庫なし。
ぶんぶん書房出版 104-0061東京都中央区銀座2-10-8 Tel 03(5550)6134
* 内科医がすすめる 「新スポーツ吹矢健康法」林督元(まさゆき)著、日本スポーツ吹矢協会発行
平成11年1月20日1999第1刷 ぶんぶn書房販売 104-0061東京都中央区銀座2-10-8
大日ビルTel 03-5550-6134 Fax 3248-0410 ¥1,200+Tax
この本は下記のと内容はほとんど同じです。
世界で実際に吹き矢がまだ狩猟に用いられているところはカリマンタン島(ボルネオ)インドネシア、
マレイシア、フィリッピン、ベネゼラ、コロンビア、パラ
グアイ、ブラジル、などではいまでも見られる
ようです。しかしそれらが何時頃 から用いられてきたのかは不明です。東南アジアの吹き矢の筒
は2メートル位の 硬い南洋鉄の木にドリルで精巧な穴を開けたもので、そのような技術が何時頃
から確立されたのか現地人でも分からないのが実情です。
弓矢の歴史は石器時代まで遡るとも
言われておりますが、吹き矢は弓矢よりも構
造的には単純な事や、筒を口にくわえる動作が極め
て原始的とも言えますので、それらを考えれば、弓矢よりも古くから用いられたのかも知れません。
日本では江戸時代に書かれた忍者の本「万川集海」の忍器篇に吹き矢の矢の図1枚が記載され
ています。また井原西鶴の書いた元禄元年1688年の日本永代蔵
にはまだ吹き矢の細工人がい
ると記されており、その頃には揚弓場、半弓場(ゲ
ームセンターのような店)で小型の弓や吹き矢
を用いたゲームが盛んだったようです。
*日本風俗史事典 弘文堂 昭和54.2.15発行 p.562
吹矢: 玩具の1種。子供ばかりでなく大人
もこれで遊んだ。元来は竹筒の中に矢を入れて鳥などを射落としていた遊技であったが、江戸時代
にはもっぱら子供の遊びになり、盛り場などでは3mもある大きな吹矢をつくり、的に矢が刺さると賞
品をだすことなど大人の遊技にもなった。江戸時代末期以後は多くは子供達が手製で作って仲間
同志で的に当てて遊んだものである。 参考 喜多川守貞「類聚近世風俗史」「守貞漫稿」 遠藤武
*遊びの大事典 (財)日本リクリエーション協会監修 東京書籍株式会社 1989.6.28
発行 p.171
* 楊弓:「楊弓場」「半弓場」「矢場」で用いれれた楊弓は柳の木で作られた弓で、弓は
2尺8寸
(85cm)矢は9寸(27cm)から9寸5分、的は3寸(9cm)− 3寸5分
(11cm)的までの距離は7間
半(14m)が定式で座射で射た。 その他に「大弓場」「機関的」などの弓技場もあった。この機関的
は「吹矢的」とも呼ばれる吹矢競技場の名称でもあった。
機関的は矢が的に当たるとひもが解けて
妖怪などが現れる仕掛けの的である。 参考:守貞漫稿 1856(嘉永6年)江原西鶴「日本永代蔵」
1688(元禄元年)
*広辞苑 岩波書店 1991.11.15発行 p.1876
鳥刺し:1.先にトリモチを塗った細い竹竿で小鳥を捕
らえること またそのようにして小鳥を捕らえ売る人 2.江戸時代鷹匠の下で鷹の餌鳥を請け負った者、
またその配下の者 3.江戸時代の遊技の1つ 。殿様、用人、鳥刺し各1枚ほかに種々の鳥の絵を
かいた13枚都合16枚の札からなり、殿様の命令によって用人が鳥刺しに鳥を捕えさせる仕組みの
もの。4.、万才の1つ 5.鳥肉のさしみ 鳥刺し竿: 鳥刺しに用いる竿。*日本語大辞典 講談社
1989.11.6発行 p.1572 鳥刺し:1.竹竿の先に鳥モチをぬり小鳥を捕らえること、またそうして鳥
を捕らえ売った人 2.民族芸能の1つ。小鳥を捕らえる動作を面白おかしく舞踊化したもの
*鳥刺し舞(山形県庄内地方)3.16枚の札を使
って鳥を捕らえる仕組みの江戸時代の遊び。
*鳥刺と吹き矢: (以下 19 Feb. 1997 大畑正弘様
<ohata@mbox.kyoto-inet.or.jp> ご教示)
*平凡社 国民百科事典 1962年4月15日初版 第6巻 404ページ 右下
ふきや 吹き矢:
息を吹いて筒に入れた矢を射る器具。南米、インドネシアな
どの未開社会では戦闘や狩猟に用
いた。マライ半島サカイ族は3-4mの竹筒に10
cm余の軽い矢を入れ巧みな呼吸で30mも吹きと
ばす。矢はシュロの葉の主脈で作り先端に毒を塗る。筒は、ボルネオでは鉄棒で木に穴をあける。
アマゾン流 域の住民はアシの茎を用いる。日本では小鳥などをとらえるのに用いたが、こ
とに江戸
時代に徳川吉宗の鷹狩り復活以来、もち竿のほか吹き矢をもって鳥
をとらえ、タカのえさとする鳥刺
の姿が知られている。この吹き矢はラッパ形に巻いた紙の羽をつけた、竹ぐしの矢を竹、木製の筒に
入れたものであった 。やがて吹き矢は盛り場の楊弓場などで、景品つきの射的として行われたり
子どもの玩具として売り出されたが、今はそれもすたれた。
(小池) 写真はシーボルトが絵師に描かせた鳥刺しをする人。(この文献を教えて下さったコンポウン
ドアーチェリストの大畑正弘様に深く感謝しております。)
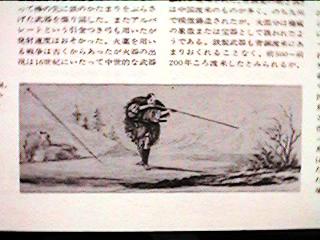
*斉藤周作さん:436静岡県掛川市中町666-4は約130年前に作られた254cm重さ2Kgもある長い
木の吹矢の筒を持っておられます。
*平塚義春さん:愛媛県大洲市新谷甲2000 山室炭店 Tel 0893-25-3935のお宅には江戸中
期のものと思われる長さ208cmの吹き矢が保存されております。表面は漆塗りの黒色で桐の木を
合わせて作ったものらしいとのことです。吹き口は5.4cmのお椀の形をしています。98.6.5
これで昔の人は鳥を捕ったりスポーツ吹矢をやったそうです。
この様にスポーツ吹矢は日本の伝統的な狩猟法とスポーツでしたがすっかり忘れ去られていました。
玩具としては世界の各地で吹き矢は珍しくない物ですが、これを武器にしていたという所はなく、日
本だけで忍者が武器として用いたように考えられている様です。私は吹き矢の威力が弓矢よりはるか
に弱いのでおそらく忍者が吹き矢を武器に用いたというのは明治以降に誰かが作り出したフィクション
ではないかと考えております。ところが上野市には横笛程度の長さで竹製の昔忍者が用いたらしい
筒があるとのことです。そのような短い筒では正確な射撃は石を投げつけるよりも効率が悪く、果たし
て実際に実戦に使用されたのかは疑問ですが、忍者がどうやって吹矢を用いたのかなど想像するこ
とは大変楽しいことです。カリマンタン島では吹き矢はすでにスポーツとして定着していますが、わが
国ではまだ子供の玩具程度のイメージでしか考えられておりません。 吹き矢は大変多くのメリットが
ある奥深いスポーツですが、今までに吹き矢をまじめにスポーツとして考えられた事はありませんでし
た。これを史上初めてスポ−ツ健康法として取り上げたのは次の本です。
*江戸時代に日本人は敬虔な仏教徒だったので魚以外にはほとんど肉食の習慣はありませんでした。
だから吹き矢は主に娯楽やスポーツとして用いられていたと考えられます。
*日本スポーツ吹矢協会会報 創刊号 1998.6.10
\50 発行 日本スポーツ吹矢協会事務局
104-0061東京都中央区銀座3-8-12大広朝日ビル5F Tel 03-3538-5837
国際吹矢道協会 http://www.sportsfukiya.net/