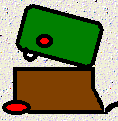 ひるねの時間
ひるねの時間
「インフラは大丈夫か?」 96/9/15
もともと人は線路に集まるのではない。列車に集まるのだ。しかし、その事を理解するのは、日本人には難しいようだ。
私には昔から、役人さん達は滅多に列車の通らない線路だけを敷いて地方の人々を騙して来た様に見えた。
しかしそうでは無い。実際に地方の人々も隣村よりも先に東京と1本のレールで結ばれた事を喜んでいたようだ。
日本人は形から入りすぎる。
いや、形に頼りすぎる。
インフラとはハードだけでなくソフトも必要なのだ。
いかに合理的な経営を行うか。
いかに理に適ったサービスを行うか。
いかにユーザーの気持ちを理解するかである。
料金が高すぎたり不便だと意味が無い。
JRが国鉄だった頃、我田引鉄という言葉が有ったそうな。地方選出の国会議員が利益誘導のために出身地に鉄道をねじ曲げて敷く事だ。
その結果、曲がりくねったり山中で行き止まりになったりする線路が沢山できた。
そうして走行に余計な時間がかかったり、ほとんど利用者のない路線が生まれ、鉄道全体の利用価値が下がった。
本当のインフラとはそんなものではない。その地域毎に合った物が有るはずだ。
大都市間を高速の幹線鉄道が結び、地域の中核都市には在来線が走り、その他の地域にはバスが走る。そして、大都市圏内では私鉄が走る。そうすればコストを押さえ本数を増やす事が出来るはずだ。
バスではなく鉄道が通ったばかりにコスト的に本数が押さえられ、余計不便になる事も多い。
インフラの整備とは本来こんなものではないと思う。
日本人の造るインフラは、形にとらわれ過ぎて無駄が多すぎる気がする。
今、建設が進む高速道路や光ファイバー網は大丈夫だろうか?
少し気になる。いや、かなり気になる。
 目次へ戻る!
目次へ戻る!