
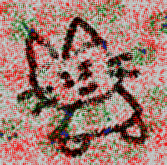 ひるねの時間
ひるねの時間
「ゴミ問題」98/11/24
ゴミの分別収集が叫ばれて久しくなる。
最初は最終処分場、つまり埋め立ての用地不足から始まり、燃えるものは極力燃やそうという事になり、次にガラスや刃物が燃えるゴミの中に入っているから、収集作業をする人が怪我をするという理由で分別が叫ばれ、それから資源のリサイクルによる有効利用という観点から、分別の種類が増え、ダイオキシン問題などで、その区別も変わった。
最近では自治体ごとに燃えるゴミと燃えないゴミとの区別が違いわかりにくい。アルミ缶とスチール缶を分別する所も有れば、資源ゴミという意識が低く、ガラスと陶器を一緒に集めている所もある。ポリスチレンは燃えるゴミなのか燃えないゴミなのか、ポリエチレンは、ポリエーテルは、塩化ビニールは、発泡スチロールは、ポリプロピレンはどっちなの?よく分からない。
どれも高温で焼却すればダイオキシンなどの有害物質は出ないものの、既存の施設に高温で焼却できる様に設計された施設が少なく、新たに建設するには費用がかかりすぎ、もし、無理に既存の施設で高温で焼却しようとすると、施設を破損し維持費がかかりすぎると言う事で焼却するのは困難らしい。
最近では生ゴミに含まれる水分が、焼却炉内の温度を下げ、余分な熱を加えないと焼却できず焼却炉を傷める原因になるとまで言われている。ここまで来てしまえば、本来ゴミを焼却して減らそうなんて考えること自体が間違っているという気がする。
企業レベルでは、もう既にゴミの出ない工場など、リサイクルの徹底がなされている所も有る。もちろん、ゴミが出ないのであるから、原料の容器や、生産時に出る副産物、消耗品はもちろんの事、事務所で使われる紙をはじめボールペンの1本までをも含む全ての事務用品、それに昼食時などに出る生ゴミに至るまで、完全にリサイクルをなしているのだ。それを可能にした秘密は、徹底したゴミの分別収集だ。
ゴミを完全に処理方法別や素材別に分ける事により、すべての行き先を明確にした。樹脂や金属、紙などは素材ごとに再生業者に、生ゴミなどは有機質肥料に、などといった風にそれぞれ処理方法にあわせて、ごみ箱の中身をそのまますぐに、業者へ引き渡せるようなかたちで収集する事に成功したからだ。
しかし、それでも最初は分別収集もうまく行かなかったそうだ。もちろん初めのうちは、ゴミを出す側の意識の低さなどが有ったかもしれない、しかしそれよりもまして問題だったのが分別に関する知識の無さだったようだ。いくら分別収集に協力したくても、例えばこのごみ箱はポリプロピレン専用と表示されていても、今、自分がゴミとして処分しようとしているものが、ポリプロピレンなのかそれ以外の素材なのか一般の人にはなかなかわかりにくいものだ。その為、分別収集に協力する意志は有っても、ついつい間違った所に入れてしまい、結局資源としてリサイクルする事を困難にしていた。
だから、ゴミを素材別よりももっと突っ込んで物別にした。どういう事かというと、例えば主原料Aの容器はそれだけで、主原料Bの容器もそれだけで、主原料Bの容器のキャップもそれだけで、という風に、数多く出るゴミは、たとえ同じ素材でも、それぞれに分別して回収する事にした。その為ごみ箱の数は30種類を越えたらしいが、こうしてしまえばいちいち素材を調べる必要も無く、勘違いなども起こりにくい。なるほど、ゴミ0も可能になるはずだ。
もちろん工場という特殊な環境におけるゴミの分別収集ということで、ゴミの種類がある程度決まっているので、この方法が可能になるわけだから、これをそのまま町内のごみ箱に適用するわけには行かない。しかし、ここまで細分化しなくても、工夫次第でリサイクル率のアップは可能だと思う。
例えば、主要な資源ゴミ数種類程度については、ごみ箱を常設するようにしてはどうだろうか?もうすでに殆どに資源ゴミにはその素材が解るマークがつけられている。素材ごとの分別は、そう困難ではないはずだ。
今現在、資源ゴミのある程度の分別収集は行われていても、その分別が不十分な事と、再生ルートが、まだ未熟でコストがかかりすぎる事などにより、結局あちらこちらの自治体で資源ゴミの山が出来ているそうだが、こういった事への対策にもなる。
また、資源ゴミの回収が1ヶ月とか2ヶ月に1回というのでは、日本の狭い住宅事情においては保管も困難で、ついつい資源ゴミを、燃えるゴミなどに混ぜて出しがちだが、常設する事によりこういった問題も解決される。
具体的には、生ゴミのよう頻繁に捨てなければならない物でもないので、ゴミ捨て場の用地確保の事も考えると、町内区画ごとにゴミ捨て場を設けなくても、歩いて5分以内程度のいくつかの町内に1ヶ所程度アルミ、鉄、PET、発泡スチロール、無色のガラス、リターナブルのビン、牛乳の紙パックなど主な資源ゴミを種類ごとに分けたゴミ箱を設けておき、その代わり常時出す事が出来るようにしておけば良いのではないだろうか。
それと、生ゴミも出来れば生ゴミのみで回収できれば、資源化の道は開けるのだが。
日本人は、過去の形式にとらわれてなかなかそこから抜け出せない。なぜか既存のシステム、つまり、まず焼却をメインに考え、焼却の出来ない物を、分別収集するというやり方にこだわっている。だから、リサイクルまで考えたゴミの分別収集が中途半端な物になっているのではないだろうか
前半にも書いたように、ゴミを分別する理由ですら、いろいろと変わってきているのだから、昔ながらの”まず焼却有りき”の考え方は、そろそろ改めたらどうだろうか?
